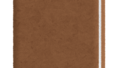みかんの木の剪定方法をご紹介します。みかんの剪定時期は、温州みかん、清美オレンジ、デコポンなど品種にかかわらず新芽が付く直前の2~3月です。4月頃になると実になる花芽が付きだしてしまうため、その前に剪定しましょう。花芽が付くまでに剪定を済ませておけば、不要な枝に養分が取られるのを防いで花芽の成長を促す効果が期待できます。
用意する道具
剪定ばさみ、または、のこぎり
剪定方法
みかんの木が幼い(1~4年)うちは、樹齢によって剪定方法が変わってきます。木を育てながら樹形づくりをしていきます。
1年目(1年生の木)
樹高を調節します。
幹を地面から約40~60cmの位置で切ります(切り戻し)。木は切り戻さないとどんどん上に伸びてしまい、新しい枝も伸びませんので今後の生長のために、勇気がいりますが思い切って切ってしまいましょう。
2年目(2年生の木)
2年目に入ると、1年目に切り戻した部分から太い枝が何本か出てきます。
この枝はみかんの木の骨格になる「主枝」とよばれる枝の候補です。
育ちのいい枝またはバランスを考えながら3本残して、残りの枝を枝元から切ってしまいましょう。
これを難しい言葉で「開心自然形」といいます。別に覚えなくてもいいです。
さらに、主枝にする枝の先端から3分の1くらいのところを切りましょう。
切った部分から「亜主枝」(副主枝、第2の主枝といった感じでしょうか)とよばれる新しい枝が出て、さらに樹形が横に広がっていきます。
3年目(3年生の木)
2年目に伸びた亜主枝のなかから何本か選んで育てていきます。
亜主枝にする枝は、なるべく地面に平行な枝を選びましょう。
なぜなら、木の樹勢(生長する力)が抑えられて実付きが良くなるからです。
上に向かってまっすぐ伸びている亜主枝は生長する力が強く、実をほとんど付けません。
なぜなら、実を付けるための栄養が枝の生長のために使われてしまうからです。
このように、まっすぐ上に伸びた亜主枝は残してもメリットがないので、枝元から切ってしまいましょう。
亜主枝は、主枝1本につき2~3本くらいを目安にするとバランスが良くなります。
これで開心自然形はほぼ完成です。
4年目(4年生の木)以降
不要な枝を取り除きます。
枝を間引く際は夏・秋に伸びた枝(夏枝・秋枝)を選んで切り落とし、春に成長した枝(春枝)は残すようにしましょう。
春枝と夏枝・秋枝の見分け方は、春枝は枝が丸い形をしていて、夏枝・秋枝は枝が三角形のような形状をしています。触ってみると良く分かりますよ。
不要な枝とは
・徒長枝:勢いよく長く伸びた枝。
・ひこばえ:樹木の根元から生えている枝。
・平行枝:近い位置で長さと太さが同じくらいの2本の枝が上下、または左右に平行して伸びている枝。
・逆さ枝:本来伸びる方向とは逆の方向(幹方向)へ伸びている枝。
・車枝:車輪の軸のように、幹の一か所から数本の枝が放射状に伸びている枝。
・立ち枝・下垂枝:字の通り、上下方向に伸びた上下枝。
・弱い枝、細い枝
以上です。最初は難しいと思いますが、気楽に、ごゆるりとやっていきましょう。